1,545 views
K:Q5、今後のウイスキーはどうなって行くのでしょうか?伺い方としては変かもしれません。ざっくり考えたのですが、ウイスキーを召し上がる方がどの様になって行くのか、増えて行くのか、あと蒸溜所が増えたり...
鈴木さん:ウイスキー全般についてですか?
K:はい。
鈴木さん:今後もどんどん商業的になっていくでしょうね。それはシングルモルトを含めてね。益々商業的になっていくというのは、私が考える方向と違う方向へ行く、という事ですけれど。
K:商業的になっていくという事は、何故商業的になっていくのでしょう?
鈴木さん:それは、商売だから商業的にならざるを得ないでしょう。
K:意味は分かるのですが、それは蒸溜所が増設している、だったり、増えているだったり、それは競争になるからですか?伺い方が難しいのですが。
鈴木さん:そうですね。ウイスキーを製造している会社もそれをつくっている職人さん、という程じゃないかもしれませんが、彼らも別に芸術品をつくろうと思っているわけではなく、商品をつくろうと思っているだけですから。売れるものをつくる、あるいは売れる状況に持って行く、これはこれからの世界状況では仕方がないでしょうね。先を見て、コマーシャリズムに乗っていかなければならない、販路を広げるために。その将来性に芸術品としての価値に対しては悲観的です。もう20世紀の様に良いウイスキーは出来ない。まあ20世紀にもいいものがつくられなかったかもしれないですが、でも19世紀のものは確認しようがないですから。ただ20世紀のウィスキーを見ていると少なくとも20世紀以降につくられたウイスキーよりもはるかにましです。正確には1980年代から乱造する時期があってその後1990年頃から良くはなっていますけれど、現場自体はより効率的になっているので、昔の様な手づくりの味わいっていうのは、薄れて行くと思います。後、自然環境が悪くなっていますしね。これはワインの世界もそうだと思うのですけれど自然環境自体は、ここ2~30年位だいぶ変化しているので、これは戻し様がないですから。
K:そうですね。
鈴木さん:それらを総合的に考えるとかつてのような素晴らしいウィスキーが今後出てくる可能性には悲観的です。まあ、20世紀の様なものは今後出来ないでしょうね。でももしかしたら全く違うより素晴らしいものが出来るかもしれない。
K:もしかしたら...?
鈴木さん:もしかしたらです。でもそれはデジタル化された別次元のウィスキーだと思います。
K:分かりました。有難うございます、確かに。
鈴木さん:その意味で20世紀のウィスキーは文化財だと思っています。今あるウイスキーは。この前山岡さんと会った時話したのですけれど本当にここ4~5年でオフィシャルのレギュラー品が凄く良くなったんですよ。ボウモアの12年だとかラフロイグの10年だとかタリスカーの10年だとか。一般的に売られているシングルモルトですね。10年20年前に比べると凄く良くなっているのですね。品質がね。でもそれは優等生的に良くなっているという意味で、前の様なガキ大将とか暴れん坊とか引っ込み思案なキャラクターとかがなくなって、個々の個性が薄れて皆優等生的になっている。
K:ええ。それは万人受けする様になっているという事ですか?
鈴木さん:そうですね。万人受けするとは言ってもアイラではきちんとピートは出しているのですよ。ピートは出しているのですけれど、昔みたいに荒っぽくもないですし、まろやかで飲みやすい。そういう意味では凄く良くなっているので今ではシングルモルトを飲むのだったらレギュラーのもので十分楽しめると思います。
K:そうですね。それは確かに。
鈴木さん:オフィシャルの通常販売されているもの、特に有名銘柄は全体にレベルが上がっています。
K:それはどうしてですか?
鈴木さん:均一化された事によって製品作りが安定されているのでしょうね。
K:ええ。その時の状態で、特にボトルが変わった時等ウイスキーの味に変化が見られ「味が少し変わった。」等追求する方もいらっしゃいますよね。
鈴木さん:私が見ている限りでは、おそらくモルトウイスキーの1番質が悪い時期は80年代なのですよ。これは時期的にいうと60年代の終わりから70年代に掛けて蒸溜所の新築、増築が行なわれ、生産の効率化が図られ、生産量が上がって大量製造が可能となった。この時期にフロアモルティングも廃止されたのですですが。結果70年代は過剰生産でストックが膨らむのですね。それで、80年代に生産調整が行われ閉鎖蒸溜所も出て来るのですけれど、この時期ってあまり良いつくりをしていないようです。品質よりも生産性優先で。その反省が90年代にちゃんとつくろうという杞憂になって来て、それがあるので80年代辺り、ここがあまり質が良くないのですね。それはおそらく蒸溜の段階でもそうだし、使っている樽なんかの質もあると思います。89年以降、又良くなってきて、それ以降つくられた原酒がオフィシャルの10年、12年、現在では18年物として出て来ているから、良くなってきたのだと思います。ただ非常に優等生的に良くなっている。かつての様な個性的、という意味で言うとちょっと違うかな、というのもありますけれど。
K:ええ。
鈴木さん:だから箱庭的。美しさはあるのですよ、以前の自然な美しさではないですが。 (5へ続く) (3へ戻る)

※当時のインタビューのまま掲載、移行しております。
但し、こちらでのサイトでの公開は、現在携わっていらっしゃる方のみにしております。
※ 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
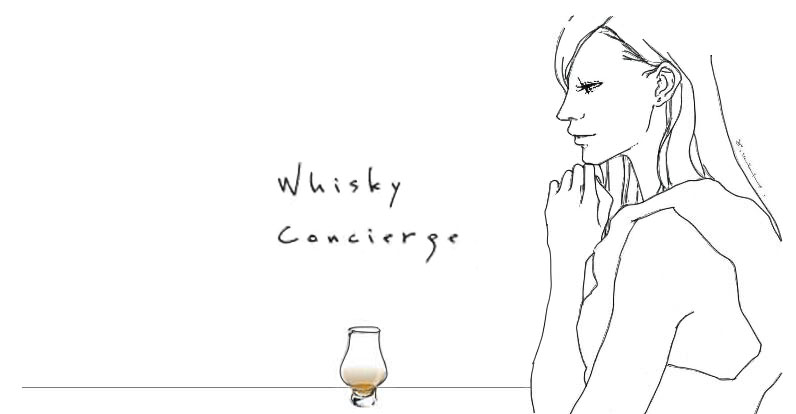

コメントを残す